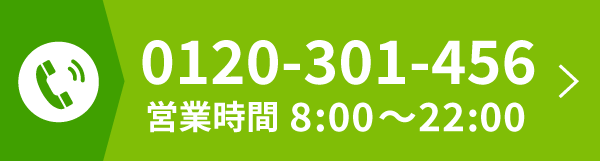「家は不動産」「車は動産」と聞いたことがある方もいっしゃるでしょう。車は動く資産です。個人で車を購入・売却する時は、家計簿等で管理されるご家庭もあるかと思いますが、法人による車の購入・売却には資産管理が必要になってきます。
こちらの記事では、法人名義の商用トラックや商用バンなど、「事業用車両」を売却する時の方法や、資産管理上での仕訳のやり方について詳しく解説します。

車の勘定科目は?事業用車両を仕訳する時の基本

事業等で使用する事業用車両の勘定科目は「車両・運搬具」となっており、固定資産として仕訳します。
物流業界で活躍する商用トラックや、営業車として商品を積載し取引先へ周る商用バンなど、法人名義の車を所有している会社は多いでしょう。車は取得(購入)してからの経過年数や、使用した走行距離等で価値が減少していきますので、その間の資産管理も必要です。
設備や車などの資産にかかった費用を、耐用年数という一定期間に配分して会計する処理のことを減価償却と言います。減価償却は、資産の取得価額が10万円以上かつ耐用年数が1年以上のものに必要な計上処理です。
事業用車両も、年数経過とともに価値が下がっていきます。車の現在の資産価値は、取得価額から各経過年ごとに減価償却費を引いて、残ったものです。毎年の減価償却費の算出方法は、取得価額を耐用年数で割り一年ごとに定額を減価償却する方法と、一年目の減価償却費が一番高くその後一定の保証額を下回ると償却率が変わる定率法、とがあります。
車を資産とした時の法定耐用年数
車両は、大きさ・種類・用途ごとに耐用年数が定められます。新車で購入した車の固定資産(車両・運搬具)としての法定耐用年数は、下記表になります。(運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用を除く)
| 減価償却資産の自動車の構造・用途(細目) | 新車購入からの法定耐用年数 |
|---|---|
| 一般用の四輪自動車(特殊自動車や運送事業用等ではない) | 6年 |
| 役員車など社用車のセダン(四輪乗用車) | 6年 |
| 総排気量が0.66リットル以下の小型乗用車 | 4年 |
| 商用バン(1ナンバーまたは4ナンバーの貨物自動車扱い) | 5年 |
上記が新車の法定耐用年数になりますが、中古車の法定耐用年数はどう決まるのでしょうか。
中古車で車を購入した場合は、それまでの車の使用状況次第で耐用年数が変わるのでは?と思われるかもしれませんが、どのように乗られていたのか確認は難しいでしょう。そのため、公平性を得るために中古車の耐用年数については簡便法が用いられます。
下記が、中古車の耐用年数の算出式になります。
新車時の法定耐用年数 - 経過年数 + ( 経過年数 × 0.2 ) = 中古車の耐用年数
車の減価償却費の計算方法
減価償却費は、定額法または定率法のどちらかの計算方法で算出します。減価償却の限度額は、除却可能な取得価額1円までと定められています。計算時には取得価額、償却率、法定耐用年数の値が必要となります。
償却率は法定耐用年数ごとに定められています。平成24年4月1日以後取得された自動車の200%定率法による償却率が、以下の表になります。
| 法定耐用年数 | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
|---|---|---|---|---|
| 6年 | 0.167 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 |
定額法の計算式
定額法の場合は、償却費の額は原則として毎年同額です。
取得価額 × 定額法の償却率 = 減価償却費/年
定率法の計算式
定率法の場合は、1年目が最も償却費の額が多く、その後は年々減少します。定率法の償却率で計算した償却額が、保証率で計算した償却保証額を下回ると、その年度から改定償却率による計算での計算式へ変わります。
1年目の定率法計算式
取得価額 × 定率法の償却率 = 1年目の減価償却費
2年目~償却保証額が下回るまでの定率法計算式
期首未償却残高 × 定率法の償却率 = 減価償却費/年
減価償却費が償却保証額を下回ってからの計算式
改定取得価額 × 改定償却率 = 減価償却費/年
事業用車両を売却する時の仕訳方法・流れ
個人事業主が事業用車両を売却する時、法人が事業用車両を売却する時、それぞれの流れや仕訳方法をご紹介します。
個人事業主が事業用車両を売却する時の仕訳方法
個人事業主が事業用車両を売却する時の流れは、まず車の売却先を検討するところから始まります。乗り換えの場合、車の購入先で下取りに出して次の車の購入資金からの値引きになるか、買取に出した際の買取代金を購入費用に充てるか、どちらかに分かれます。車の状態や車種にもよりますが、一般的に商用車は中古車市場で需要が高く人気のため、買取に出すと高額で売却できる可能性があります。下取りと買取どちらも同時に見積もりを取ってよりお得な方はどちらか、しっかり確認しましょう。
個人事業主が所有している営業車などを売却する時に、気を付けなければならない点をいくつかご紹介します。事業用の経費とプライベートな生活費とを区別して帳簿に付ける必要があります。
事業用車両を売却した時の売却益は「事業主借」、売却損は「事業主貸」に仕訳します。下取りに出した場合は、下取り価格が帳簿価額を上回れば売却益、下回って入れば売却損です。
個人事業主が事業用車を売却する時の直接法による仕訳(※免税の場合)
例として、200万円で購入した営業用5ナンバー車両を売却するときの会計とします。
| 借方勘定科目(金額) | 貸方勘定科目(金額) | 概要 |
|---|---|---|
| 減価償却累計額(150万円) | 車両運搬具(50万円) | 購入額-売却までの減価償却累計額=車両運搬具(車の期首帳簿価格) |
| 売却価額(70万円) | 預託金(1.2万円) | 預託金はリサイクル預託金のこと |
| 事業主借(18.8万円) | 売却価額-車両運搬具-リサイクル預託金=売却益(事業主借) |
個人事業主が事業用車両を売却すると、売却先の下取業者もしくは車買取業者へ車を譲渡したことになります。そのため、売却時の売却益は課税対象となり、確定申告が必要になります。この譲渡時に得た利益のことを「譲渡所得」と言いますが、譲渡所得には取得から5年以内に売却した場合の「短期譲渡所得」と、取得から5年以上経過後に売却した場合の「長期譲渡取得」があります。税額は短期と長期で異なり、短期譲渡所得の方が税金が高額になります。譲渡所得には特別控除制度があり、売却益が全体を通して50万円以下であれば、課税対象外となります。
※売却の売上高が1,000万円以下の個人事業主の場合は、消費税が免除となります(条件として適格請求書発行事業者ではないこと)。
法人が事業用車両を売却する時の仕訳方法
法人が事業用車両を売却した時の仕訳方法は、利益が出た場合は「固定資産売却益」、損失が出た場合は「固定資産売却損」として処理されます。課税対象となる法人の場合は、売却金額のみ課税取引にあたります。リサイクル料金は非課税になります。
法人が事業用車を売却する時の仕訳(※課税あり、税込み処理の場合)
例として、200万円で購入した営業用5ナンバー車両を売却するときの会計とします。
| 借方勘定科目(金額) | 貸方勘定科目(金額) | 概要 |
|---|---|---|
| 減価償却累計額(150万円) | 車両運搬具(150万円) | 売却までの減価償却累計/不課税車両本体 |
| 売却価額(70万円) | 車両運搬具(50万円) | 車の売却代金/課税対象の車両本体 |
| 預託金(1.2万円) | リサイクル預託金 | |
| 固定資産売却益(18.8万円) | 売却益 |
最新の国産トラックの特徴や共通点は

事業用車両の売却時の仕訳方法について解説しましたが、近年の運輸業・輸送業等の商用車や商用トラック市場の動向はご存知でしょうか。日本自動車工業会による2024年度の普通トラック市場動向調査によると、一部の運輸業ではコロナ禍以降の経営状況は好転してきているものの、好転は少数派となっており、燃料価格やエネルギー価格の高止まりも要因となって経営が圧迫される事業所も多いようです。ただ、その中でも商用トラックには最先端技術の開発が進められています。
運輸業・輸送業界で活躍する最新トラックに共通する特徴をこちらでご紹介します。
高レベルな安全運転支援機能を搭載しドライバーをサポート
最新型トラックに搭載される、「ドライバーの安全運転をサポートする機能」が年々向上しています。トラック(総重量3.5トン超えの大型トラック)を対象に搭載が義務付けられている衝突被害軽減ブレーキ機能だけでなく、アクセルとブレーキを踏み間違えた場合の衝突回避支援機能や、障害物を検知できるセンサーによって障害物を感知した時にアラートする機能など、多様な機能が各トラックメーカーによって開発されています。
また、製造メーカーごとにシステムは異なりますが、車両と自動車製造メーカーが通信を行い、稼働中のサポートを行うネットワークコンテンツも続々と開発されています。例えば日野自動車のネットワーク「HINO-CONNECT」は、安全装置が作動した場合に車両近くにドライバーがいなくても、日野自動車のサポートセンターから車の契約しているお客様本人へ直接メールで連絡が入るように設定されています。緊急時には、お客様専用Webサイトから車両の現在位置の確認が可能で、救助を求める際の目印にもなります。
低燃費!環境に配慮されたエネルギーで動くトラック
トラックは自身の車重だけでなく積載量によってさらに重くなるため、その重量を支える車体も含め、トラックが走るためには大きなパワーを必要とします。大きな動力を生み出す動力源として、トラックにはこれまでもディーゼルエンジンが載せられていることが多くなっていました。
ただディーゼルエンジンというと短時間で高回転のため、少ない燃料で大きな燃焼力を持ち燃費が良いことがメリットではあったものの、排出ガスに粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)が多く含まれることにより、環境への影響が大きいとされてきました。しかし、それからディーゼルエンジンの燃料は開発が進められ、環境性能に配慮したクリーンバイオディーゼルによって、排気ガスがクリーンで二酸化炭素排出量も少なく、環境負荷が低い燃料が登場しました。このクリーンディーゼルの開発によって、高回転(トルク)で力強さを持ちながら、クリーンで環境性能が高いトラックが増えてきています。
例えば、日野自動車の2トントラックデュトロは、2.0トンクラスのトラックにディーゼルエンジン&DPR-Ⅱトラックを搭載していて、パワーだけでなくクリーン性能も高いトラックです。排出ガス基準値も規制値を超えないことから、平成28年に制定された自動車NOx・PM法の基準適合車となっています。
準中型免許は18歳、大型・中型自動車免許の受検資格は19歳から可能に!
トラック運転者不足の改善に向けて、運転免許制度の改定や、新たな免許の新設がありました。トラックドライバーの平成29年3月の法改正により、準中型免許という免許区分が新設されました。準中型免許は18歳以上から取得できる免許で、車両の準中型トラック(5トンまで)が運転できる免許となっています。また、令和4年5月に改正道路交通法があり、受験資格特例教習の修了(36時限以上)により19歳から、大型自動車免許と中型自動車免許の受験が可能になっています。

まとめ
こちらの記事では、事業用車両を所有する個人事業主または法人が、その車両を売却する時の仕訳の仕方等について詳しく解説しました。車は経費ではなく固定資産となっていますので、購入から売却までしっかりとした管理が必要です。車の購入や売却を検討されている場合は、是非参考にご覧ください。